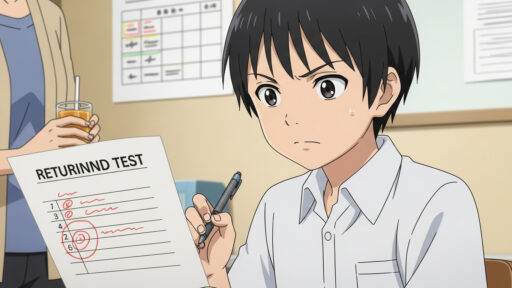
こんにちは、初石駅前校です。
定期テストの結果が返却されると、一喜一憂しがちですが、最も大切なのはその結果を「次に繋げる」ことです。特に中学生になると、学習内容が複雑になり、ただ問題を解き直すだけでは成績は伸びにくくなります。
「頑張っているのに点数が伸びない」という場合、それは復習の「やり方」に原因があるかもしれません。流山市、柏市周辺の中学校でも、定期テスト後の復習方法に悩む生徒が多く見られます。
今回は、テスト結果を次の成長の糧にするために、保護者様が中学生のお子様に身につけさせてあげたい効率的な復習計画の立て方と3つの視点を解説します。
📖 目次
データで見る復習の効果
定期テスト後の復習が、次のテストにどれだけ影響するかを示すデータをご紹介します。
- 復習実施率と成績向上の関係: テスト返却後1週間以内に復習を行った生徒は、復習をしなかった生徒と比較して、次回のテストで平均15点高い得点を取るというデータがあります(ベネッセ教育総合研究所)
- 間違い直しの効果: 間違えた問題を3回以上繰り返し解いた生徒は、1回だけ解き直した生徒と比較して、同じ問題での正答率が約80%向上します(東京大学教育学部研究)
- 見直しノートの活用: 間違えた問題をまとめた「見直しノート」を作成し定期的に復習する生徒は、作成しない生徒と比較して、定期テストの平均点が約12点高いという調査結果があります(学研教育総合研究所)
- エビングハウスの忘却曲線: 人間は学習後1日で約70%を忘れるため、テスト返却後すぐに復習することで、記憶の定着率が約3倍向上します(心理学研究)
これらのデータは、復習の「タイミング」と「やり方」が成績向上に直結することを示しています。
テスト結果を次に繋げるための3つの視点
1. 「失点箇所」を3つのタイプに分類する
点数が伸び悩む最大の原因は、「失点の理由」を曖昧にしたまま、全範囲を漠然と復習することです。まずは間違えた問題を以下の3つのタイプに分類させましょう。
A. 知識不足: そもそも単語や公式を覚えていなかった
- 復習のポイント: 暗記の徹底。一問一答形式で確認し直す
- 具体例: 英単語のスペルミス、歴史の年号忘れ、数学の公式が出てこない
- 対策: 単語帳や一問一答集を使い、覚えるまで繰り返す
B. ケアレスミス: 符号や単位ミス、問題の読み間違いなど
- 復習のポイント: 集中力の改善。次はどこに注意するかをメモする
- 具体例: 計算ミス、問題文の読み飛ばし、符号の付け忘れ
- 対策: ミスした箇所に付箋を貼り、「次はここを確認する」と具体的に書く
C. 思考力不足: 応用問題や初見の問題で、解法が思いつかなかった
- 復習のポイント: 類題演習。基礎に戻り、なぜその公式を使うのかを理解する
- 具体例: 文章題が解けない、初見の問題で手が止まる
- 対策: 基礎問題に戻り、解法のパターンを理解してから類題に挑戦
お子様と一緒にテストを分析し、A→B→Cの順番で復習計画を立てることで、効率よく弱点を克服できます。
2. 「復習の期限」を必ず設ける
人間の記憶は時間と共に薄れていくため、「気が向いたときにやる」という復習では効果が半減します。
ヒント: テスト返却後1週間以内に「知識不足(タイプA)」の復習を終え、次の1ヶ月以内に「思考力不足(タイプC)」の類題演習を終えるなど、具体的な期限を設定させましょう。
復習期限の目安:
- タイプA(知識不足): テスト返却後1週間以内
- タイプB(ケアレスミス): 次のテスト2週間前までに対策を考える
- タイプC(思考力不足): テスト返却後1ヶ月以内に類題演習を完了
期限を設けることで、「後でやろう」という先延ばしを防ぎ、記憶が新しいうちに効率的に復習できます。
3. 「見直しノート」を作成する習慣を定着させる
点数アップに直結するのは、「間違えた問題」だけをまとめた自分専用の弱点集です。
やり方: 間違えた問題とその正しい解き方、失点タイプを1冊のノートにまとめます。定期的にこのノートを見返すことで、次回のテスト前に何をすべきかが明確になり、効率的な総復習が可能になります。
見直しノートの作り方:
- 左ページ: 間違えた問題を貼るか書き写す
- 右ページ: 正しい解き方と、失点タイプ(A・B・C)を記入
- 色分け: タイプA=赤、タイプB=青、タイプC=緑など色で分ける
- 見返し日: ノートの最初のページに「復習予定日」を記入
この「見直しノート」は、高校受験の直前期にも最強の復習ツールとなります。
復習スケジュールの立て方
効果的な復習スケジュールの例をご紹介します。
テスト返却後1週間(記憶が新しいうちに)
- 全科目のテストを見直し、失点箇所をA・B・Cに分類
- タイプA(知識不足)の復習を最優先で実施
- 見直しノートの作成開始
テスト返却後2週間〜1ヶ月(定着期)
- タイプB(ケアレスミス)の対策を考える(チェックリスト作成など)
- タイプC(思考力不足)の類題演習を実施
- 見直しノートを週1回見返す
次のテスト2週間前(総復習期)
- 見直しノートを中心に復習
- 前回間違えた問題が解けるか確認
- 新しい範囲の学習と並行して、弱点を克服
効果的な復習ができているかチェックリスト
お子様の復習方法が効果的かどうか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
□ テスト返却後1週間以内に復習を始めている
記憶が新しいうちに復習することが重要です。
□ 間違えた問題を3つのタイプ(A・B・C)に分類している
失点の理由を明確にすることが成績向上の第一歩です。
□ 見直しノートを作成している
自分専用の弱点集が最強の復習ツールです。
□ 復習の期限を具体的に決めている
「いつか復習する」では効果が半減します。
□ 知識不足(タイプA)から優先的に復習している
暗記で解決できる問題から片付けることが効率的です。
□ ケアレスミス(タイプB)の対策を具体的に考えている
「次は気をつける」では改善しません。具体的な対策が必要です。
□ 思考力不足(タイプC)の問題は類題演習をしている
基礎に戻り、解法のパターンを理解することが重要です。
5個以上チェックできれば、効果的な復習ができています。3個以下の場合は、今回ご紹介した3つの視点を実践してみてください。
よくあるご質問
Q. 復習する時間がないのですが、どうすればいいですか?
A. まずはタイプA(知識不足)の復習だけでも行いましょう。暗記で解決できる問題は、短時間でも効果があります。1日10分でも、テスト返却後1週間続けることで大きな差が生まれます。
Q. 見直しノートを作る時間がもったいない気がします。
A. 見直しノート作成は「時間の投資」です。次回のテスト前に、何を復習すべきか一目で分かるため、総復習の時間が大幅に短縮されます。長期的には時間の節約になります。
Q. ケアレスミスはどうすれば減らせますか?
A. ケアレスミスは「気をつける」だけでは減りません。具体的な対策として、「問題文に線を引く」「計算の途中式を省略しない」「見直しの時間を5分確保する」など、行動レベルで決めることが重要です。
Q. 思考力不足(タイプC)の問題が多いのですが、どう復習すればいいですか?
A. まずは基礎問題に戻り、公式や解法のパターンを理解し直しましょう。その後、同じレベルの類題を3問以上解くことで、解法が身につきます。いきなり応用問題に挑戦するのではなく、段階を踏むことが大切です。
• テスト返却後1週間以内の復習で次回平均15点向上
• 間違えた問題を3つのタイプ(知識不足・ケアレスミス・思考力不足)に分類
• 復習の期限を具体的に設定することが効果的
• 見直しノート作成で定期テスト平均点が約12点向上
• A→B→Cの順番で復習計画を立てる
• エビングハウスの忘却曲線: 1日で約70%を忘れる
まとめ
保護者様は、点数そのものよりも、「テスト分析」と「復習計画」を立てるプロセスをサポートし、お子様の自己管理能力と学習の質を高めていきましょう。
テスト結果を次に繋げるためには、ただ問題を解き直すだけでなく、「なぜ間違えたのか」を明確にし、タイプ別に対策を立てることが重要です。今回ご紹介した3つの視点と見直しノートの活用で、次回のテストでは必ず成果が出ます。
当塾でも、定期テスト後の復習指導と見直しノートの作成サポートを行っています。流山市、柏市周辺で学習面のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
塾長より


