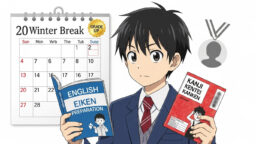こんにちは、初石駅前校です。
2025年1月実施の大学入学共通テストから、「情報I」が新設され、文系・理系を問わずすべての高校生にとって必須科目となります。プログラミングやデータ分析など、新しい分野を含むため、多くの受験生と保護者様が「何を、どう対策すればいいのか」と大きな不安を感じています。
しかし、「情報I」は、対策を立てて集中的に学習すれば、むしろ他の受験生と差をつけるチャンスでもあります。流山市、柏市の高校生も、適切な対策により「情報I」を得点源にしています。今回は、高校生が効率的に「情報I」の対策を進めるための完全ガイドをご紹介します。
📖 目次
情報Iについてよくある質問
Q. 情報Iは文系でも受験必須ですか?
A. はい、2025年1月実施の共通テストから、文系・理系を問わず全受験生が受験必須です。国公立大学を志望する場合、情報Iの得点も合否に影響します。文系だからといって軽視せず、しっかり対策しましょう。
Q. プログラミング経験がないのですが、大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。「情報I」は、プログラミング技術そのものよりも、「情報社会の仕組み」「データの活用法」「論理的思考の原理」といった基礎的な概念の理解が問われます。最初から本格的なコーディングをする必要はありません。
Q. 学校の授業だけで対策は十分ですか?
A. 学校の授業は基本ですが、共通テスト対策としては不十分な場合が多いです。試作問題や予備校の予想問題を数多く解き、問題の形式に慣れることが重要です。特に、アウトプット(問題演習)に重点を置いた学習が効果的です。
Q. いつから対策を始めるべきですか?
A. 高2の冬休みから始めるのが理想的ですが、高3からでも遅くはありません。新しい科目のため過去問が少ないですが、試作問題や予想問題を繰り返し解くことで、十分に対策できます。
出題分野別の対策法
情報Iの主要な出題分野と、それぞれの効果的な対策法をご紹介します。
1. 情報社会の問題解決
出題内容: 情報モラル、著作権、個人情報保護、ネットワークの仕組み
対策法: この分野は暗記が中心です。日常生活での情報リテラシーに関する問題が多く、常識的に考えれば解ける問題も多いです。教科書や参考書で基本用語を確認し、試作問題で出題形式に慣れましょう。
重要キーワード: 著作権法、個人情報保護法、情報セキュリティ、ネットワークプロトコル、暗号化
2. データの活用
出題内容: データ分析、統計、グラフの読み取り、相関関係
対策法: 数学の統計分野と重複が多いため、数学の知識を活用できます。平均、中央値、標準偏差などの基本的な統計量を理解し、グラフから情報を読み取る練習をしましょう。
重要キーワード: 平均、中央値、分散、標準偏差、相関係数、散布図、ヒストグラム
3. コンピュータとプログラミング
出題内容: 二進数、論理回路、アルゴリズム、プログラミング(主にPython)
対策法: 最も重要なのは「原理・原則」の理解です。具体的なコーディングよりも、二進数、論理回路、アルゴリズム(流れ図)など、すべての基盤となる原理を徹底的に理解することが高得点への近道です。
冬休みの活用: プログラミング分野は、実際に手を動かすことで理解が深まります。最初からPythonなどの本格的な言語に取り組む必要はありません。Scratch(スクラッチ)のようなビジュアルプログラミング環境や、共通テスト対策用の専用アプリで、「条件分岐(if文)」や「繰り返し(for文)」といった基礎的な論理構造を体験的に理解することが効果的です。
重要キーワード: 二進数・十進数変換、論理演算(AND, OR, NOT)、アルゴリズム(流れ図)、変数、条件分岐、繰り返し
4. 情報通信ネットワークとデータベース
出題内容: ネットワークの仕組み、データベースの基本、SQL
対策法: ネットワークの基本的な仕組み(IPアドレス、DNS、プロトコルなど)とデータベースの基礎(表の構造、検索、並べ替え)を理解しましょう。SQLの基本的な構文(SELECT, WHERE, ORDER BY)も重要です。
重要キーワード: IPアドレス、DNS、プロトコル、データベース、テーブル、SQL、検索、並べ替え
情報I対策チェックリスト
情報Iの対策が進んでいるか、確認してみましょう。
□ 試作問題を1回分解いて、現在の実力を把握している
まずは現状把握が重要です。
□ 二進数・十進数の変換ができる
プログラミング分野の基礎中の基礎です。
□ 論理演算(AND, OR, NOT)を理解している
論理回路の問題で必須の知識です。
□ アルゴリズム(流れ図)が読める
条件分岐や繰り返しの流れを追えるようにしましょう。
□ 基本的な統計量(平均、中央値、標準偏差)を理解している
データ分析分野で頻出です。
□ 著作権や個人情報保護の基本を理解している
情報社会の問題解決分野で出題されます。
□ Scratchやプログラミングアプリで実際に手を動かしている
体験的に学ぶことで理解が深まります。
□ 問題演習をインプットの3倍の時間をかけている
アウトプット重視が合格の鍵です。
□ 試作問題や予想問題を複数回解いている
問題形式に慣れることが重要です。
□ 苦手分野を特定し、重点的に対策している
弱点を放置せず、集中的に克服しましょう。
7個以上チェックできれば、対策は順調です。5個以下の場合は、今すぐ対策を始めましょう。
NG学習法とOK学習法の比較
情報Iの学習で、効率が悪い方法と効率が良い方法を比較してみましょう。
学習の進め方
NG学習法: 教科書を最初から最後まで読み込む。用語を全て暗記しようとする。
OK学習法: まず試作問題を解いて、出題傾向を把握する。頻出分野に絞って集中的に学習する。
理由: 新しい科目のため、全てを網羅しようとすると時間が足りません。頻出分野に絞ることで、効率的に得点力を上げられます。
プログラミングの学習
NG学習法: いきなりPythonの本格的な参考書を読み、複雑なコードを書こうとする。
OK学習法: Scratchやビジュアルプログラミングで「条件分岐」「繰り返し」の概念を体験的に理解する。共通テスト対策用のアプリを活用する。
理由: 共通テストでは、本格的なコーディング技術よりも、プログラミングの基本的な論理構造の理解が問われます。
時間配分
NG学習法: インプット(教科書を読む)に多くの時間を使い、アウトプット(問題演習)はほとんどしない。
OK学習法: インプット1: アウトプット3の割合で学習する。概念理解に1時間使ったら、問題演習に3時間使う。
理由: 新しい科目はインプットに時間をかけがちですが、「情報I」はアウトプット(問題演習)が鍵です。試作問題や予想問題を数多く解き、問題の形式に慣れることが、直前期の不安解消に繋がります。
対策の開始時期
NG学習法: 「新しい科目だから、まだ様子見」と後回しにする。
OK学習法: 高2の冬休みから、または高3の春から計画的に対策を始める。冬休みのまとまった時間を活用する。
理由: 新しい科目だからこそ、早めに対策を始めることで、他の受験生と大きく差をつけられます。柏市、流山市の高校生も、早期対策で「情報I」を得点源にしています。
📌 この記事のポイント
軽視せず、しっかり対策しましょう。
□ 最も重要なのは「原理・原則」の理解
二進数、論理回路、アルゴリズムが基盤です。
□ 冬休みを利用してプログラミング思考を掴む
Scratchやアプリで体験的に学びましょう。
□ 学習計画は「インプット1: アウトプット3」
問題演習に重点を置くことが合格の鍵です。
まとめ
「情報I」は、これからの社会で必須の力を問う科目です。適切な対策で、確実な得点源にしましょう。
最も重要なのは「原理・原則」の理解、冬休みを利用して「プログラミング思考」を掴む、効率的な学習計画は「インプット1: アウトプット3」、この3つを実践することで、情報Iを得点源に変えることができます。流山市、柏市の高校生も、適切な対策により「情報I」で高得点を獲得しています。
当塾でも、共通テスト「情報I」の対策講座や、効率的な学習計画の作成をサポートしています。情報I対策でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
塾長より