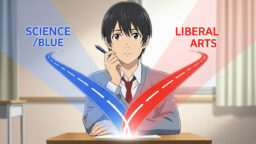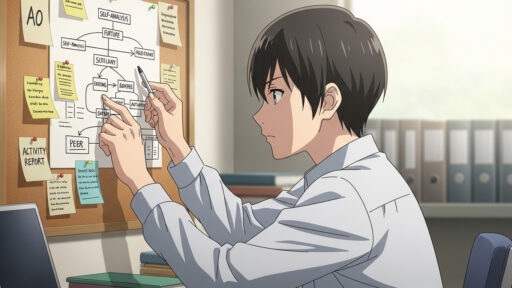
こんにちは、初石駅前校です。
大学入試において、従来の一般選抜(学力試験)に加えて総合型選抜(旧AO入試)の重要性が増しています。この選抜方式は、学力だけでなく、高校生活での活動や意欲、明確な将来の目標を評価するものです。
「総合型選抜は高3になってから考える」と思われがちですが、実は高1・高2からの計画的な準備が合否を大きく左右します。特に、この方式で求められる「主体性」や「思考力」は、付け焼き刃では身につきません。流山市、柏市周辺の高校でも、総合型選抜を利用する生徒が年々増加しています。
今回は、高1・高2のお子様と保護者様が知っておくべき、総合型選抜の正しい準備手順と、合否を分ける「自己分析」の進め方を解説します。
📖 目次
データで見る総合型選抜の現状
総合型選抜の利用状況と、その重要性を示すデータをご紹介します。
- 総合型選抜の利用率: 令和6年度の私立大学入学者のうち、約15%(約6万人)が総合型選抜で合格しており、10年前の約2倍に増加しています(文部科学省「大学入学者選抜実施状況」)
- 難関私立大学での増加傾向: 早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学などの難関私立大学でも、総合型選抜の募集人員が年々増加しており、一部の学部では定員の20%以上を総合型選抜で募集しています(各大学公式発表)
- 評定平均の重要性: 総合型選抜の出願条件として、評定平均4.0以上を求める大学が約60%、3.5以上を求める大学が約30%となっており、高校の成績が重視されています(大学入試センター調査)
- 活動実績の評価: 総合型選抜で合格した学生の約80%が、部活動・生徒会・ボランティア・資格取得のいずれかで具体的な実績を持っていたというデータがあります(予備校調査)
これらのデータは、総合型選抜が「楽な入試」ではなく、計画的な準備が必要な選抜方式であることを示しています。
高1・高2から始める! 総合型選抜の正しい準備手順
Step 1: 早期に「自己分析」を始める(高1推奨)
総合型選抜で最も重要なのは、「なぜその大学・学部に入りたいのか」を明確に言語化できることです。これは、自己分析を通じてしか得られません。
ポイント:
- 過去の経験を振り返り、「何に興味を持ち、なぜそれを頑張れたのか?」を洗い出す
- 失敗や挫折した経験も含めて、その時の「行動原理」を掘り下げる
- 自己分析で見つけた興味と目標に沿って、その後の高校生活の活動を選ぶ
自己分析は高1の早い時期から始めることで、高校3年間を一貫したストーリーで語ることができ、面接官に「計画性のある生徒」という印象を与えられます。
Step 2: 評価される「活動実績」を積み重ねる(高1・高2)
明確な目標に基づいた活動は、面接や提出書類で高い評価を得られます。単なる参加ではなく、活動から何を学び、どう成長したかが問われます。
評価される活動例:
- 部活動: 部長・副部長などの役職、県大会出場、チームへの貢献など具体的な成果
- 生徒会活動: 生徒会役員として学校行事の企画・運営、課題解決への取り組み
- ボランティア活動: 地域貢献、福祉活動、環境保護など継続的な参加と具体的な貢献
- 資格取得: 英検2級以上、TOEFL、数学検定、簿記検定など志望分野に関連する資格
- 研究活動: 探究学習、課題研究、科学オリンピック、論文コンテストなど
重要なのは、活動から「何を学び、どう成長したか」を言語化し、記録しておくことです。高3になってから思い出そうとしても、具体的なエピソードは忘れてしまいます。
Step 3: 基礎学力を疎かにしない(常に重要)
総合型選抜は、学力試験がないため「楽な入試」だと誤解されがちですが、実際は高校の成績(評定平均)が重視されます。また、面接や小論文では、基礎学力が土台にある上での思考力が問われます。
注意点:
- 定期テストに真剣に取り組み、評定平均4.0以上を目安に維持する
- 一般入試への切り替えも視野に入れ、基礎力定着の学習は高2までに終える計画を立てる
- 小論文対策として、読書習慣を身につけ、時事問題に関心を持つ
- 面接対策として、自分の考えを論理的に説明する練習をする
総合型選抜で不合格になった場合、一般入試に切り替える必要があります。そのため、総合型選抜の準備と並行して、基礎学力の維持は絶対に怠らないようにしましょう。
合否を分ける「自己分析」の進め方
総合型選抜で最も重要な「自己分析」を、具体的にどう進めるかを解説します。
自己分析の3つのステップ
ステップ1: 過去の経験を書き出す
- 小学校から現在までの経験を時系列で書き出す
- 楽しかったこと、頑張ったこと、悔しかったことをすべて記録
- なぜその経験が印象に残っているのかを考える
ステップ2: 共通点を見つける
- 書き出した経験の中から、共通するテーマやパターンを探す
- 「人の役に立つことが好き」「新しいことに挑戦するのが好き」など、自分の価値観を明確にする
- 失敗した経験から学んだことも含めて整理する
ステップ3: 将来の目標と繋げる
- 自分の価値観と興味を踏まえて、将来やりたいことを考える
- その目標を実現するために、どの大学・学部で何を学ぶ必要があるかを調べる
- 志望理由を「過去の経験→現在の興味→将来の目標」というストーリーで語れるようにする
総合型選抜準備チェックリスト
高1・高2のお子様が総合型選抜の準備を順調に進められているか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
□ 自己分析を始めている
過去の経験を振り返り、自分の興味や価値観を明確にしています。
□ 評定平均4.0以上を維持している
定期テストに真剣に取り組み、高い成績を保っています。
□ 継続的な活動実績がある
部活動・生徒会・ボランティアなど、何か一つ継続している活動があります。
□ 活動の記録を残している
活動から学んだことや成長したことを記録しています。
□ 志望分野に関連する資格取得に挑戦している
英検、TOEFL、数学検定など、計画的に資格取得を進めています。
□ 読書習慣がある
小論文対策として、様々なジャンルの本を読んでいます。
□ 志望大学・学部の情報を調べている
オープンキャンパスに参加したり、大学のホームページで情報収集しています。
5個以上チェックできれば、総合型選抜の準備は順調です。3個以下の場合は、今すぐ準備を始めましょう。
よくあるご質問
Q. 総合型選抜と学校推薦型選抜(指定校推薦)の違いは何ですか?
A. 学校推薦型選抜(指定校推薦)は、高校からの推薦が必須で、評定平均が基準を満たせば合格率が非常に高い方式です。一方、総合型選抜は、高校からの推薦は不要で、志望理由書・面接・小論文などで総合的に評価されます。倍率も高く、準備が不十分だと不合格になる可能性があります。
Q. 総合型選抜で不合格になったら、一般入試に切り替えられますか?
A. はい、可能です。ただし、総合型選抜の結果発表は11〜12月頃のため、一般入試の準備期間が短くなります。そのため、総合型選抜の準備と並行して、基礎学力の維持は絶対に怠らないようにしましょう。
Q. 高3から総合型選抜の準備を始めても間に合いますか?
A. 不可能ではありませんが、非常に厳しいです。総合型選抜では、高校3年間の活動実績や評定平均が評価されます。高3から準備を始めると、活動実績が不足し、志望理由も説得力に欠ける可能性が高いです。高1・高2から計画的に準備することを強くおすすめします。
Q. 評定平均が3.5しかありません。総合型選抜は諦めるべきですか?
A. 評定平均3.5でも出願できる大学はあります。ただし、選択肢は限られるため、今からでも定期テストに力を入れ、評定平均を少しでも上げる努力をしましょう。また、活動実績や志望理由書で強い印象を与えることで、評定平均の不足を補うことも可能です。
• 総合型選抜の利用率は10年前の約2倍に増加
• 評定平均4.0以上が出願条件の大学が約60%
• 高1から自己分析を始めることが重要
• 活動実績は「何を学び、どう成長したか」が問われる
• 基礎学力の維持は絶対に怠らない
• 総合型選抜と一般入試の両方に対応できる準備を
まとめ
総合型選抜は、受験生にとって「自分を深く理解し、未来を設計する」貴重な機会です。計画的に準備を進め、合格を掴み取りましょう。
高1・高2からの計画的な準備が、総合型選抜の合否を大きく左右します。自己分析、活動実績、基礎学力の維持という3つの柱をバランスよく育てることが、成功への近道です。
当塾でも、総合型選抜の準備サポート、志望理由書の添削、面接対策を行っています。流山市、柏市周辺で総合型選抜を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
塾長より