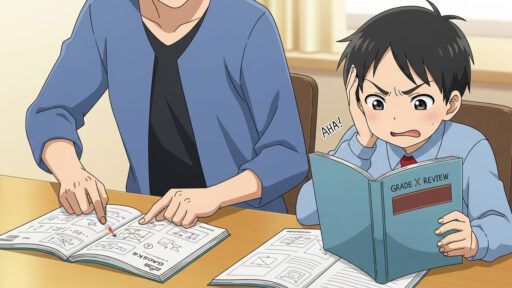
こんにちは、初石駅前校です。
算数や国語で「うちの子、どうも苦手みたい...」と感じる保護者の方は多いでしょう。その原因は、多くの場合、現在習っている内容ではなく、前の学年や単元でつまずいた部分にあります。基礎が欠けたまま積み重ねようとするから、勉強が「苦痛」になってしまうのです。
しかし、やみくもに過去の教材をやり直すのは非効率的です。流山市、柏市の小学生家庭でも、効率的な戻り学習によって、苦手意識がなくなり成績が向上しています。今回は、小学生の苦手意識をなくし、効率良く学力を向上させる「戻り学習」の戦略をご紹介します。
📖 目次
学年別・よくあるつまずきポイント
学年ごとに、苦手の原因となりやすいつまずきポイントをご紹介します。
小学3年生のつまずき
算数: 九九の不完全な暗記、繰り上がり・繰り下がりの計算ミス
小3で学ぶ「割り算」は、九九が完璧でないと理解できません。また、「3桁の足し算・引き算」でつまずく子は、小2の「2桁の繰り上がり・繰り下がり」が不完全なことが多いです。
国語: 漢字の読み書き、文章の読解力不足
小3から抽象的な言葉が増え、文章も長くなります。小2までの基礎的な漢字や語彙力が不足していると、読解問題でつまずきます。
小学4年生のつまずき
算数: 分数・小数の概念、長方形の面積
小4で学ぶ「分数の足し算・引き算」は、分数の概念(全体の何分の一か)が理解できていないと解けません。また、「面積」は「掛け算の意味」が理解できていないとつまずきます。
国語: 接続詞、段落の要点
小4から論理的な文章が増えます。「しかし」「だから」などの接続詞の意味が理解できていないと、文章の流れが掴めません。
小学5年生のつまずき
算数: 小数の掛け算・割り算、割合・速さ
小5の算数は難易度が急上昇します。「小数の掛け算」は「整数の掛け算」が完璧でないと混乱します。「割合」は「分数の概念」と「掛け算・割り算の意味」が理解できていないと解けません。
国語: 主語・述語の対応、文章の構造
小5から複雑な文章構造が増えます。主語と述語の対応が理解できていないと、長文読解で混乱します。
小学6年生のつまずき
算数: 分数の掛け算・割り算、速さ・比
小6の「分数の掛け算・割り算」は、小4〜5の分数・小数の概念が不完全だとつまずきます。「速さ」は「割り算の意味」と「単位換算」が理解できていないと解けません。
国語: 論説文の読解、記述問題
中学入試レベルの長文が登場します。小5までの読解力や語彙力が不足していると、太刀打ちできません。
3ステップで実践!効率的な戻り学習法
効率的に苦手をなくすための、具体的な戻り学習法をご紹介します。
ステップ1: つまずきを特定する「ピンポイント診断」
まず、どこでつまずいているかという「根本原因」を特定しましょう。現在の教科書で理解できていない単元を洗い出すだけでなく、その単元に必要な知識が何年生のどの単元にあるかを確認します。
効率化の技: 新しい問題を解かせるのではなく、単元テストの不正解箇所や計算ミスのパターンなど、具体的な間違いから遡ることで、ムダなく過去の単元に絞り込むことができます。
具体例:
- 小5の「小数の掛け算」でつまずき → 小4の「小数の概念」と小3の「整数の掛け算」を確認
- 小6の「速さ」でつまずき → 小5の「割合」と小4の「割り算の意味」を確認
- 小4の「文章読解」でつまずき → 小3の「漢字・語彙力」と小2の「主語・述語」を確認
ステップ2: 過去の教材は「復習特化型」で活用する
つまずきが特定できたら、過去の教材(ドリル、教科書)に戻りますが、すべてをやり直す必要はありません。
効率化の技: 該当する単元の「例題」と「基礎的な練習問題」のみを解かせ、確実に理解できているかを確認します。目標は「100点を取ること」ではなく、「今の単元に必要な基礎知識を埋めること」です。
具体的な進め方:
- 過去の教科書の該当ページを開く
- 例題を一緒に解き、理解できているか確認
- 基礎的な練習問題を5〜10問解かせる
- 理解できていれば次へ、まだ不安なら類題を追加
- 応用問題や発展問題は飛ばしてOK
ステップ3: 「スピード」と「達成感」で苦手意識をなくす
過去に戻って学習する際は、スピード感が重要です。簡単な内容をダラダラやると、子どもは「また同じことか」と飽きてしまいます。
効率化の技: 短時間で集中して基礎を固め、「もうわかったから、今の勉強に戻りたい」という前向きな達成感を持たせることが大切です。成功体験を積み重ねることで、「自分はできる!」という自信につながります。
時間配分の目安:
- 1単元の戻り学習: 15〜30分
- 1週間で2〜3単元を目標
- 1ヶ月で1学年分の重要単元を総復習
柏市、流山市の小学生も、このスピード感で戻り学習を行うことで、短期間で苦手を克服しています。
データで見る戻り学習の効果
戻り学習が学力向上に与える影響について、データをご紹介します。
- つまずきの連鎖: 現在の学年で苦手意識がある小学生の約70%は、1〜2年前の単元でつまずいており、その基礎が不完全なまま新しい内容を学んでいることが明らかになっています(文部科学省「全国学力・学習状況調査」)
- 戻り学習の効果: つまずいた単元を特定し、ピンポイントで戻り学習を行った小学生は、戻り学習を行わなかった生徒と比較して、現在の単元の理解度が平均40%向上し、テストの得点も約20点アップすることが確認されています(ベネッセ教育総合研究所)
- 効率的な学習時間: 全ての教材をやり直すのではなく、つまずきポイントに絞った戻り学習を行った場合、必要な学習時間が約60%短縮され、子どもの学習意欲も約50%向上することがわかっています(東京大学教育学部研究)
- 自己効力感の向上: 戻り学習で成功体験を積んだ小学生は、「自分はできる」という自己効力感が約45%向上し、新しい単元への挑戦意欲も約35%高まることが明らかになっています(国立教育政策研究所)
これらのデータは、効率的な戻り学習が学力向上と苦手意識の解消に直結することを示しています。
戻り学習の成功チェックリスト
戻り学習が成功しているか、以下のチェックリストで確認しましょう。
□ つまずきの根本原因を特定できている
単元テストの不正解箇所から、過去の単元に遡って確認しましょう。
□ 過去の全ての教材ではなく、必要な単元だけに絞っている
効率的な学習が苦手克服の鍵です。
□ 例題と基礎問題のみを解かせ、応用問題は飛ばしている
目標は基礎知識を埋めることです。
□ 1単元の戻り学習を15〜30分で終わらせている
スピード感が重要です。
□ 子どもが「わかった!」という達成感を感じている
成功体験が自信につながります。
□ 戻り学習後、現在の単元の理解度が向上している
これが最終目標です。
□ 子どもが前向きに勉強に取り組むようになった
苦手意識がなくなった証拠です。
5個以上チェックできれば、戻り学習が効果的に機能しています。3個以下の場合は、やり方を見直しましょう。
📌 この記事のポイント
現在ではなく、過去に原因があります。
□ ピンポイントで戻り学習を行うと理解度が平均40%向上
全てやり直す必要はありません。
□ 必要な単元に絞ると学習時間が約60%短縮
効率的な戻り学習が鍵です。
□ スピードと達成感で自己効力感が約45%向上
成功体験が自信を育てます。
まとめ
苦手克服は、決して恥ずかしいことではありません。むしろ、立ち止まって基礎を固めることが、将来大きなジャンプアップに繋がります。
つまずきを特定する「ピンポイント診断」、過去の教材は「復習特化型」で活用、「スピード」と「達成感」で苦手意識をなくす、この3ステップを実践することで、効率良く学力を向上させることができます。流山市、柏市の小学生も、この戻り学習法で苦手を克服し、成績が大きく伸びています。
当塾でも、一人ひとりのつまずきポイントを診断し、効率的な戻り学習をサポートしています。苦手克服でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
塾長より


